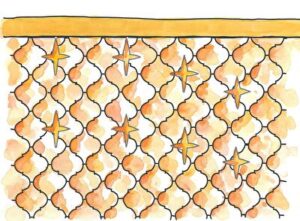ランドスケープ・デザイナー 横山裕幸さん
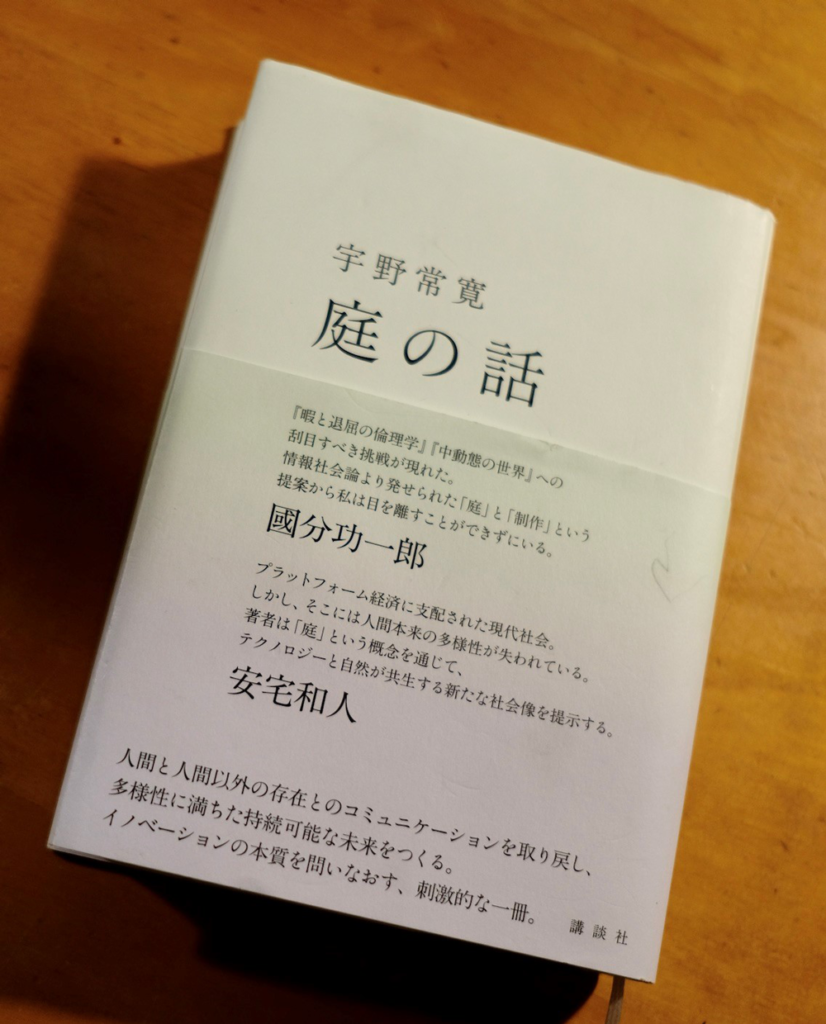
庭って何だろう?って問われてもなかなかうまく答えることができないのではないでしょうか。それほど曖昧模糊とした世界と言えるのかもしれません。「家」ほど求められる役割が明確ではなく、こうあるべきだという規範もはっきりしない場と言えそうです。その分からなさ捉えどころのなさを埋めるように坪庭だの雑木の庭だのイングリッシュ・ガーデンだのポタジェだの、様々な庭のスタイルを分類することによって私たちは庭を捉えようとしてきました。それでも「家庭」という言葉が「家」と「庭」からなるように、「庭」は「家」と同じように私たちの暮らしにとって不可欠なものです、にも関わらずこれまでの私たちは「家」にばかり目が行っていたようです。そんな「庭」は現代において非常に見えづらい場なのですが、つい最近まさに「庭の話」という本を書かれた方がいます。
著者はサイバー空間やSNSの世界についての批評を書いてこられた宇野常寛さんで、誰もに平等に開かれた人と人との関わりを醸成してくれると思われていたサイバー空間やSNSの世界が「炎上」や「分断」という言葉が示すように殺伐とした空間になりつつある今を受けて、私たちが目指すべき社会のモデルは実空間としての「庭」にあるのではないかという仮説を提案してくれています。宇野さんが説く庭は①人間が人間外の事物とのコミュニケーションを取るための場であり②人間外の事物同士がコミュニケーションを取り外部に開かれた生態系を構築している場であり③人間はその生態系に関与はできるけれど、支配することはできない場であり④人間が孤独で居ることができる場である。というものです。
庭の歴史をひもとくと、自給自足のための修道院の庭、瞑想・黙考するための寺院の庭、多様な生きものたちと共に生きるためのエコロジカル・ガーデンなど様々な庭のかたちを見ることができます。宇野さんの視点はこれまでのどのかたちとも異なる、人と人との関わり、人と事物との関わりなど、コミュニケーションのための庭というものです。
それほど遠くない過去に私たちが期待を込めて描いたサイバー空間やSNSの世界は論破するしない、勝った負けたといった人と人とのぎくしゃくとした関係を生み出し、実世界ではまさかと思われていた戦争が世界のあちこちで起こっている現在、庭が持つ人と人、人と事物との静かなコミュニケーションの場という価値が現在においてこそ求められているのではないでしょうか。