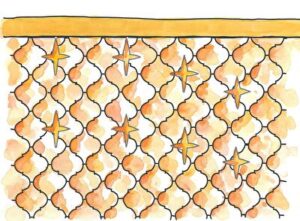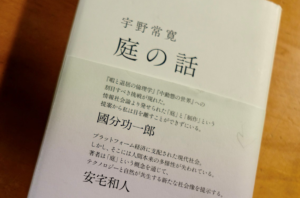提携建築士 永添 一彦さん
東京で地震の怖さを経験した東日本大震災から14年余りが経ちました。その後も熊本地震、北海道胆振東部地震、能登半島地震、最近では鹿児島県トカラ列島の群発地震など、列島各地で続いています。われわれ建築士は築年数の経った建物の相談に伺うことも多いのですが、現在の耐震基準から考えると残念ながら十分とは言え
ません。なぜなら、これまでの大地震とその建物被害の究明による耐震基準の強化の積み重ねを経て今があるからです。
まず1978年宮城県沖地震後の1981年の建築基準法改正(新耐震基準)があげられます。改正前は震度5レベルの地震で倒壊しないという基準でしたが、新耐震基準では震度6強~7レベルの大地震でも倒壊しないよう強化され、木造住宅では必要な筋交いなど耐力壁の量が増強されました。
次が1995年の阪神淡路大震災後の2000年の法改正です。この大震災では特に木造住宅の倒壊よる圧死の割合が大きく、木造住宅の耐震性確保の一大転換点となりました。木造住宅の領域でも構造実験が行われるようになり、実務者レベルでも経験や勘だけに頼らない構造設計という考え方が広まり始めました。建築基準法には(1)地盤と基礎(2)柱や梁等の軸組の接合部の補強(3)耐力壁の配置のバランスについて、確認方法も含め具体的に明記されました。
3つ目は、2000年施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)により、建設会社は構造耐力上主要な部分と雨水の侵入について10年間の瑕疵担保責任を負うことが定められたのですが、2009年10月施行の住宅瑕疵担保履行法により瑕疵保険に加入することが義務付けられました。保証会社の検査員は施工基準通りかチェックするため、新築毎に2回現場で検査します。今日の新築住宅全般の品質確保に有効に働いています。
2025年4月にも改訂がありました。昨今ソーラーパネルの設置の有無や、建物の高さや外装建材の種類に応じた地震力の算定方法が整備され、個々の実情に沿った耐震設計が出来るようになりました。
2000年以降、特に2009年10月以降の木造住宅は施工内容も含め安心できる内容と思いますが、それ以前の住宅も耐震補強を行うことで現行レベルにアップデートできます。